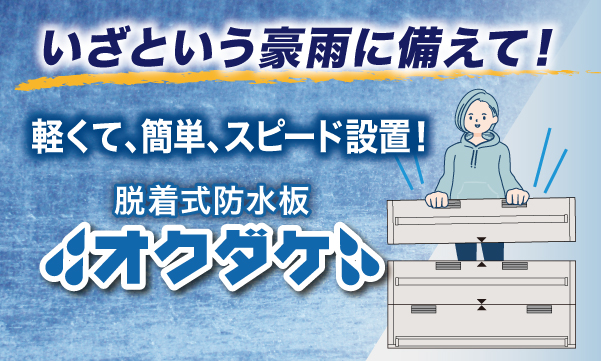文部科学省の手引に学ぶ、子どもたちの安全を守る方法

この記事では、文部科学省の水害対策手引に基づいた学校施設の水害対策と事例について詳しく解説します。
なぜ今、学校施設の浸水対策が急務なのか

学校は子どもたちの学びの場であると同時に、災害時には地域住民の避難場所としての重要な防災拠点でもあります。全国の公立学校のうち、約91%が災害対策基本法などに基づく避難所に指定されています。平成28年の熊本地震では、366校が避難所として利用され、実際に使われた避難所の約半数が学校でした。
しかし、西日本を中心に記録的な豪雨災害をもたらした平成30年7月豪雨では667校が物的被害を受け、水浸しになった教室や体育館で机や教材が散乱し、床や壁に泥が堆積するなど深刻な被害に見舞われました。さらに、休校が1~2か月に及んだケースや完全な復旧までに1年以上を要した事例もあり、避難所としての機能を十分に果たせなかった学校が存在したと考えられます。
参考:文部科学省|老朽化対策・防災対策を踏まえた学校施設の整備等について
浸水対策が追いついていない学校の現状
文部科学省の2020年の調査によると、全国の公立学校のうち7,476校が浸水想定区域内に立地し、要配慮者利用施設として位置づけられています。
ところが、浸水対策が実施されているのは1,102校(14.7%)、受変電設備の浸水対策が完了しているのは1,125校(15.0%)にとどまっており、約85%が未実施の状況であることがわかりました。
大規模な水害が発生した際は、子どもたちの安全や教育環境が深刻な危機にさらされる可能性はもとより、避難所としての機能を維持できず、地域の防災対策にも大きな影響を与える恐れがあります。
この調査結果は、国が学校施設の水害対策を喫緊の重要課題として認識し、具体的な支援策の検討を急ぐきっかけとなりました。
文部科学省が示す「水害対策の手引」3つのステップ

近年の気候変動による災害の激甚化を受け、国は従来の堤防やダムなどの河川整備を中心とした治水対策から、流域全体で総合的に水害を防ぐ「流域治水」への転換を図っています。
こうした国の方針を受け、文部科学省は令和5年に「水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進のための手引」を策定しました。
この手引を参考に、学校施設の水害対策を「水害リスクの確認」「浸水対策の計画策定」「具体的な対策の実施」の3つのステップでまとめました。
参考:内閣官房|防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策
ステップ1:水害リスクの確認
(ハザードマップ、過去の浸水実績の確認)
まず学校周辺の水害リスクを把握し整理します。
● 洪水ハザードマップ(河川の氾濫による浸水想定)
● 内水ハザードマップ(下水道の排水能力を超えた雨水による浸水想定)
● 高潮ハザードマップ(台風等による海水の浸水想定)
● 発生頻度ごとの浸水想定図(年超過確率また別の想定水深)
● 過去の浸水履歴(実際に発生した浸水被害の記録)
これらの情報を基に、リスクを「見える化」することで適切な水害対策の計画策定につなげます。
ハザードマップの詳しい読み方や活用方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:ハザードマップとは?意味や種類・使い方・調べる際に押さえるポイントを解説
ステップ2:浸水対策の計画策定(目標設定、優先順位の決定)
把握した水害リスクに基づき、具体的な浸水対策の目標計画を以下のように2つに分けて設定します。
目標①:緊急時の児童生徒等の安全確保のための対策
目標②:学校教育活動の早期再開のための対策
また、対策の方向性については「浸水深は大きくないが発生頻度が高い場合」はハード面の対策を基本とし、「想定浸水深は大きいが発生頻度が低い場合」は、事前避難等のソフト面の対策を前提に決定します。これらを判断するには、建設コストと維持管理コストのバランスを考慮した総合的な検討が求められます。
<ハード対策(施設・設備の整備)>
● 受変電設備のかさ上げ:電気設備の浸水を防ぐ
● 防水板(止水板)の設置:出入口からの浸水を防ぐ
● ピロティによる高床化:建物自体を浸水レベルより高くする
● 重要諸室の保護:給食室や職員室などの上階移動 など
<ソフト対策(運用・教育面)>
● 避難確保計画の作成・見直し:緊急時の避難手順を明確化
● 平時からの点検・確認体制の構築:日常的な備えと管理体制
● 児童生徒への防災教育:水害に関する知識と対応力の向上 など
これらの対策を学校の立地条件や想定される浸水リスクに応じて最適に組み合わせることが、効果的な浸水対策につながります。
ステップ3:具体的な対策の実施

「オクダケ」は設置後も出入口の扉を開閉できるため、防水性能を確保しつつ人の通行が可能。
避難時や救助活動時にも適した構造となっている。
効果的なハード対策の例をご紹介します。
| 対策 | 具体例 | 目的 |
| 受変電設備のかさ上げ・移設 | 受変電設備を2階に移設 | 浸水による電気設備の故障を防ぎ、教育活動の早期再開を可能にする。 |
| 防水板(止水板)の設置 | 校舎の出入口や地下室の入り口に防水板を設置 | 外部からの浸水を防ぎ、建物内部の被害を軽減 |
| ピロティによる高床化 | 新築校舎において、1階部分をピロティ構造(柱だけの空間)にして、教室を2階以上に配置 | 建物自体を浸水レベルより高く保つ |
| 重要諸室の保護 | 給食室や職員室、保健室などを2階以上に移設 | 災害時でも学校運営の中枢機能を維持しやすくする |
敷地や変電設備のかさ上げなどの対策は、学校の建て替えや大規模改修(長寿命化改良)を行うタイミングで、計画的に実施することが求められます。また、構造設計や外構設計においては、浸水対策を考慮した基準階高や排水計画の設定が必要です。
かさ上げや高床化が難しい場合に建物内部への浸水を防ぐうえで注意すべき場所は、出入口や窓などの「開口部」です。開口部は浸水に対して脆弱な場所であり、想定される浸水水位に対応した防水対策を講じることが求められます。
このような場所への防水板(止水板)の設置は、既存の建物にも比較的容易に導入できることから、短期的に高い効果を発揮します。特に、受変電設備(キュービクル)や非常用発電設備などの重要な施設への浸水を防止することで、被害を最小限に抑え、早期復旧につなげることができます。
まとめ
学校施設の浸水対策は、激甚化する水害から子どもたちの安全を守り、地域の防災拠点としての機能を維持するための重要な課題となっています。
対策にはハード面とソフト面の両輪での取り組みが不可欠ですが、特に既存施設に導入しやすい開口部への対策が急がれています。そのなかでも、防水板(止水板)の設置は、出入口からの浸水を効果的に防ぐ実用的な方法です。
鈴木シャッターでは、学校をはじめとした公共施設や民間施設にも数多くご採用いただいています。簡易脱着式防水板の「オクダケ」のほか、防水板「アピアガード」シリーズとしてさまざまなタイプを取り揃えており、製品仕様のご案内や導入事例のご紹介、現地調査のご相談も承っております。浸水対策をご検討の際は、お気軽に鈴木シャッターまでご相談ください。