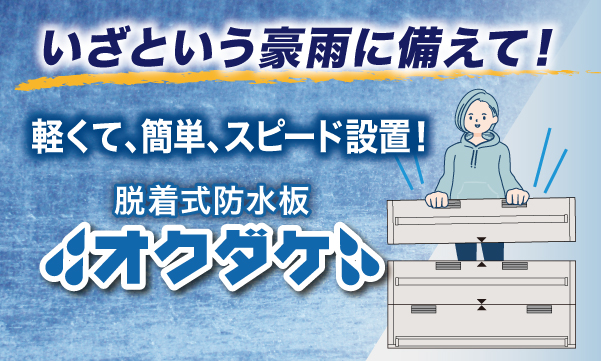目 次
2025年9月の浸水事故から学ぶ、地下駐車場における水害対策の重要性

出典:国土交通省
2025年9月12日、三重県四日市市の地下駐車場で発生した大規模浸水事故は、地下施設の水害対策における重大な教訓を私たちに示しました。1時間当たり123.5mmの猛烈な雨により、地下2階と地下1階が浸水し、274台もの車両が水没する事態となりました。
この事故の背景には、防水板の故障を約3年9カ月も放置していたという管理上の問題がありました。国土交通省によると、2021年12月の時点で管理会社から故障の報告を受け、修理の実施について協議中だったものの、実際の修繕には至らなかったといいます。結果として、記録的な豪雨の際に防水板が作動せず、浸水被害の拡大を招きました。
このように、不具合を認識していながら対応を先延ばしにすることは、管理体制上の重大なリスクです。定期点検を実施しても、指摘された不具合を放置すれば、事故発生時に「予見できたのに防げなかった」として、管理責任を問われる可能性があります。 適切な水害対策と日常的な管理体制の構築が、施設と利用者の安全を守る上で重要です。
なぜ浸水は起きたのか?地下施設に潜む危険性

出典:国土交通省
四日市市の地下駐車場で発生した浸水事故の原因は一つではなく、以下のように複数の要因であったことが確認されています。
●想定を超える局地的な豪雨の発生
●防水板(止水板)の管理・機能不全
四日市市で観測された1時間当たり123.5mmという猛烈な雨は観測史上最大の記録でした。ハザードマップは過去のデータに基づく予測であり、それを超える豪雨が発生するリスクは常に存在します。企業のBCP(事業継続計画)では、ハザードマップの想定にとどまらず、より厳しい状況を想定した対策を講じる必要があります。
出典:気象庁|日本の気候変動2025 5.降水
また、防水板の故障が約3年9カ月もの間放置されていたことに加え、夜間に記録的な大雨が短時間で発生したため、迅速な対応が難しい状況でした。防水板は、地上との出入口10か所に設置されており、このうち車両用出入口3か所(電動式)では2か所が故障、残る1か所は急激な浸水により操作が間に合わず、さらに歩行者用出入口7か所(手動式)でも防水板の設置が間に合いませんでした。
今回の事例を教訓として、適切な備えを講じることが、施設と利用者の安全を守る第一歩となります。
今すぐ始めるべき防水板(止水板)の適切な管理方法

防水板を確実に機能させるためには、設置後の継続的な点検と、緊急時を想定した訓練の両立が欠かせません。これらを実施し、いざという時に確実に機能する水害対策体制を構築する必要があります。
定期的なメンテナンスによる性能維持
防水板は、設置して終わりではなく、継続的な点検と整備で性能を保つことが重要です。まずは、外観や作動の状態を定期的に確認し、故障や劣化がないかを確認します。故障や劣化があった場合には、シーズン前までに修理しなければなりません。
防水板は、設置して終わりではなく、継続的な点検と整備で性能を保つことが重要です。まずは、外観や作動の状態を定期的に確認し、故障や劣化がないかを確認します。故障や劣化があった場合には、シーズン前までに修理しなければなりません。
製品によってはメーカーによる専門点検や部品交換が必要となる場合もあります。その際は取扱説明書やメーカーが定める点検周期を参考に、確実な対応を心がけましょう。また、保管場所が屋外である場合など、環境によっては劣化が早まることがあるため、点検頻度の調整が求められます。
たとえば、防水板に使用されている防水ゴム(止水ゴム)は消耗品です。防水ゴムには硬化やひび割れ、切れ目といった劣化のサインが現れます。目視で変形や損傷が認められた場合は、直ちに交換が必要となります。なお、鈴木シャッターでは3年に1度の防水ゴム交換を一つの目安として示しています。
定期的な設置訓練で作業に慣れる
防水板は「いざという時に誰でも、迅速に、正しく」設置できる状態にしておく必要があります。定期的に行う防災訓練などを活用し、以下のポイントを確認しましょう。
| ポイント | 確認内容 |
|---|---|
| 場所の確認 | 防水板や部材の保管場所と、実際に設置する場所を全員で共有する |
| 手順の確認 | 実際に設置してみて、作業手順に不明な点や問題がないか確認する |
| 時間の計測 | 設置に何人でどのくらいの時間がかかるかを計測し、記録しておく |
| 判断・指示体制の確認 | 誰の判断で設置を開始し、誰が作業を指揮・実施するのかを明確にしておく |
一つの方法として、設置手順を動画で記録して共有することで、担当者が不在でもスムーズな設置が可能になります。
・防水板の寿命を延ばす保管のコツとメンテナンスの目安(「浸水対策ナビ」マガジンNo.22へ)
設備に加え、運用で備える体制づくり

せっかく防水設備を導入しても、運用体制が整っていなければ緊急時に機能しない可能性があります。誰が・いつ・どう動くかを明記した手順書とや、防水板をすぐに取り出せる保管場所の確保が不可欠です。
設置手順書と行動ルールの整備
豪雨による浸水は予測が難しく、夜間や休日にも発生するため、気象情報の収集と判断をする人・設置者の役割分担と、24時間365日対応可能な連絡・出動体制を整えておく必要があります。
手順書やルールは専門用語を避け、誰でも理解できる内容にし、動画などで設置手順を共有することで、管理人や住人自身でも迅速に行動できる仕組みを整えましょう。
迅速な設置を可能にする保管場所の確保
人が手動で設置するタイプの防水板は、防水板の保管場所が設置場所から離れていたり、物置の奥深くに置いていたりすると、浸水が始まってからでは手遅れになる危険性があります。保管場所から設置場所までの距離を把握する、または保管場所を設置場所の近くにして、誰でもすぐに取り出せるようにしておくことが大切です。
▼持ち運びが不要なシートタイプ防水板はコチラ
・採用実績1,500台!シートタイプの防水板が選ばれる3つの理由とは?
(「浸水対策ナビ」マガジンNo.7へ)
まとめ
地下駐車場に限らず、特に都市部では商業施設や駅構内、オフィスビルなど、多くの地下施設が存在しており、そこには想像以上に多くの水害リスクが潜んでいます。被害を未然に防ぐには、設備の導入だけでなく適切な管理体制の構築が不可欠です。 気候変動により想定を超える豪雨が頻発する現代において、防水板の定期的なメンテナンス、設置訓練の実施、そして明確な行動ルールの整備が被害を最小限に抑える鍵となります。設備と人による運用体制の両輪を整えることで、施設と利用者の安全を守り、事業継続性を確保することができるでしょう。